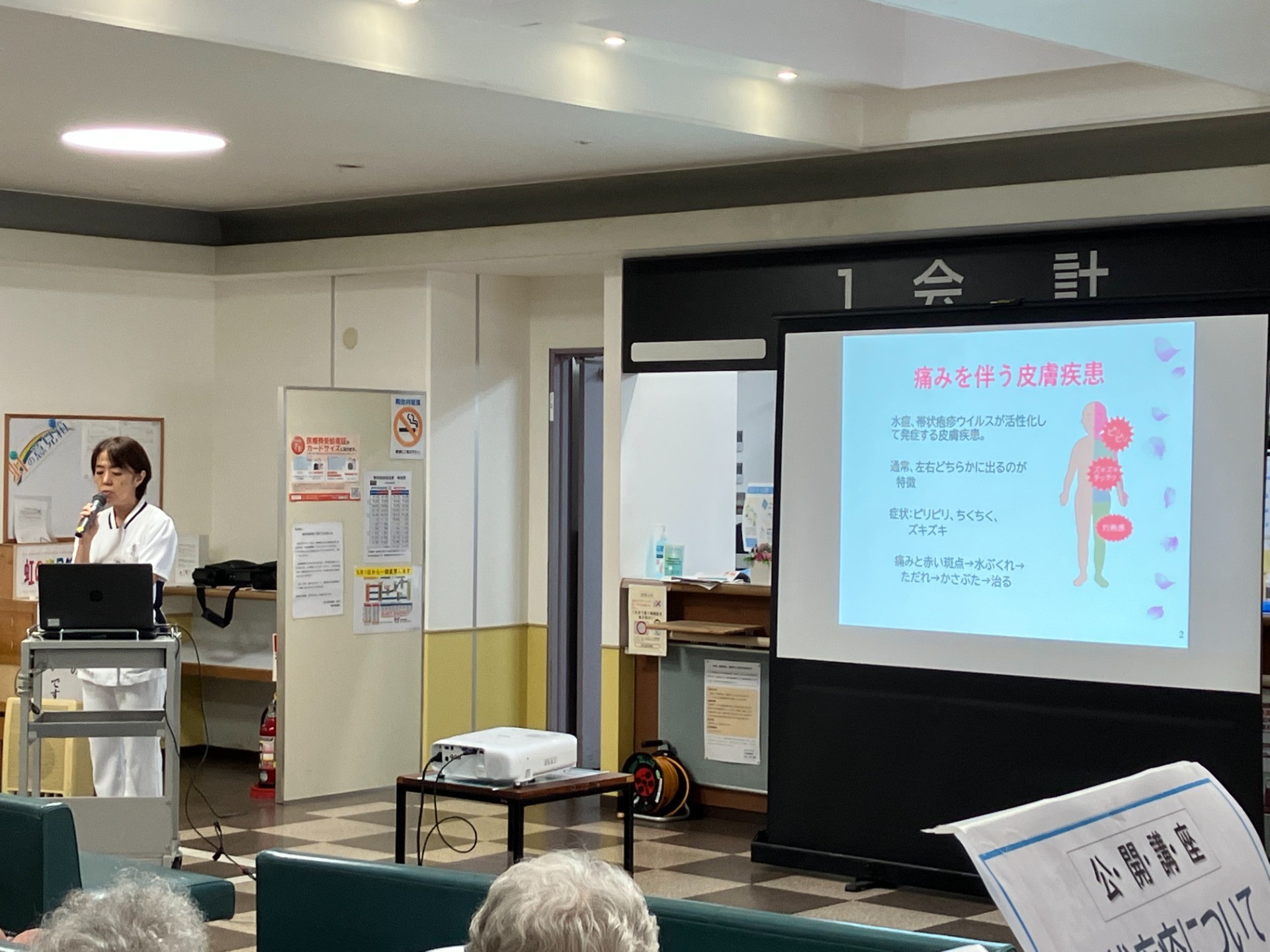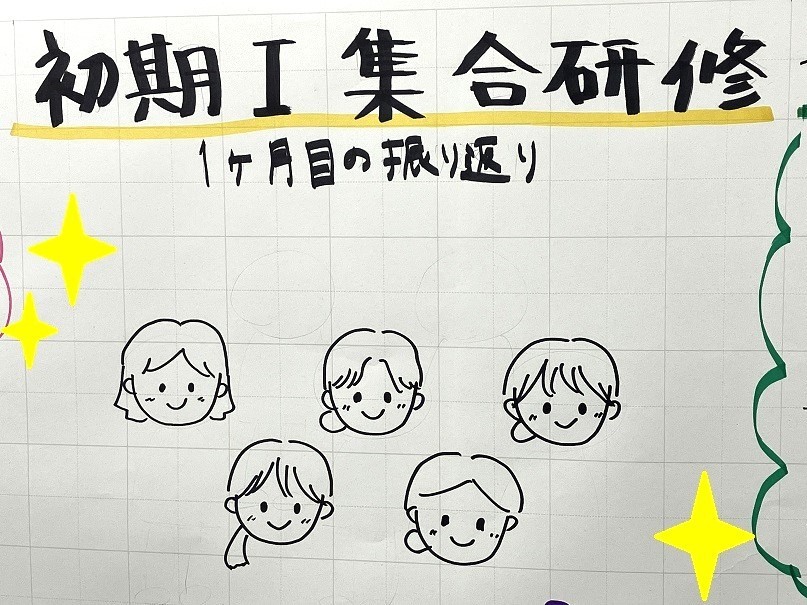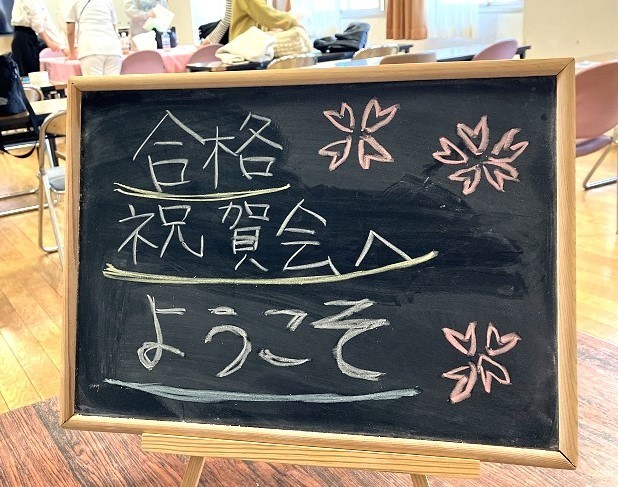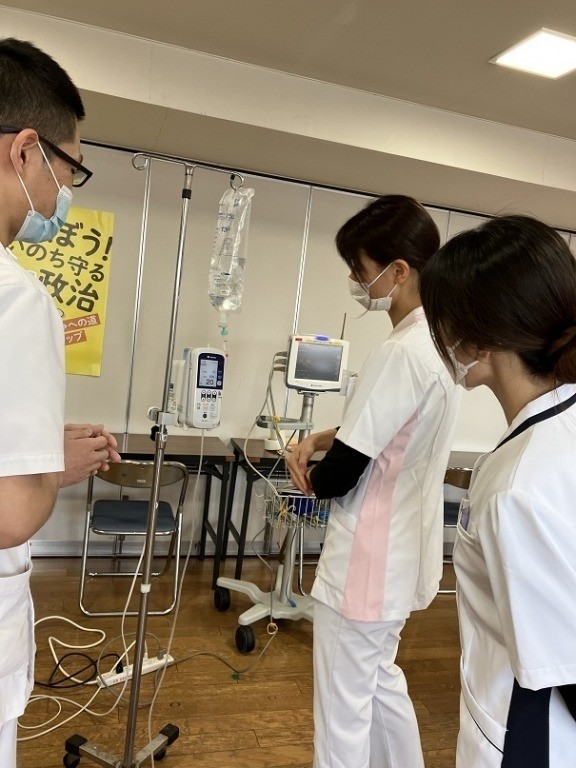-
イベント
☆ 2025年度 看護師復職支援セミナー開催します ☆
-
イベント
2025年☆インターンシップ・ナーシングセミナー開催!!
-
イベント
2/1(土)・3/1(土)看護師復職支援セミナー申込 ♪♪ (カムバックナースセ...
-
きらり看護学生
12,1月号「看護の現場より その人らしさを支える看護を目指して 共立病院」
-
きらり看護学生
10,11月号「がんばれ! 1年目看護師」
-
ブログ
ナーシングセミナー報告☆
-
きらり看護学生
8.9月号 看護の現場より「自宅で過ごしたいと願う患者さんに寄り添って」
-
ブログ
外来公開講座☆
-
ブログ
6月の1年目研修「口腔ケア」
-
きらり看護学生
6.7月号「1年目看護師奮闘記 ~入職して1か月!~」
-
きらり看護学生
12,1月号「看護の現場より その人らしさを支える看護を目指して 共立病院」
-
きらり看護学生
10,11月号「がんばれ! 1年目看護師」
-
きらり看護学生
8.9月号 看護の現場より「自宅で過ごしたいと願う患者さんに寄り添って」
-
きらり看護学生
6.7月号「1年目看護師奮闘記 ~入職して1か月!~」
-
きらり看護学生
4,5月号「新入生のみなさん!入学おめでとう♪」
-
きらり看護学生
【きらり看学生】2024年2,3月号
-
きらり看護学生
【きらり看学生】2023年12,1月号
-
きらり看護学生
【きらり看学生】2023年10,11月号
-
きらり看護学生
【きらり看学生】2023年8,9月号
-
きらり看護学生
【きらり看学生】2023年6,7月号